”子どもたちの課題”というタイトルにしましたが、早速訂正。
正確にいうならば、社会全体の課題…ではないかと感じています。
図書室にいると、”よく来る子”と”全然顔を見ない子”がいます。
皆さんも、学生時代を思い返してみてください。
図書室…行っていましたか?(笑)
そして、全く来ない子どもたちの中には、結構な確率で本を「読めない」「選べない」子がいるのです。
普段から文字を目にしているのに、なぜ読めないのか?
どうして自分が読みたい本を選べないのか?
司書先生として、その解決策を考えます。
情報過多の時代に埋もれる「読む力」
最近、友人の話を聞いて驚いたことがあります。
「うちの娘、ドラマを1,5倍で見ているんだよね。」

アラフォーの私は仰天しました。
ドラマや映画って、間を楽しんだり演者のさりげない動作を観察したりして楽しむものじゃないの?
もちろん、ストーリーを追うことも重要だけど、それだけじゃないでしょ?
でも、子どもたちを取り巻く社会は、もうそれが当たり前のようです。
動画サイトを開けば、ショート動画が溢れています。
もちろん、子どもたちの目をひくものは他にもありますよね。
店頭には魅力的なゲームが所狭しと並べられ、
スマホには年代問わず、しかも短時間で楽しめるアプリが満載です。
しかもそれらは、使えば使うほどパーソナライズされて子どもたちに届けられます。
こんな情報社会において、わざわざ店頭まで行き、物言わぬ静かな本と出会うのは至難の業。
実際に子どもたちに趣味は?と聞いて「読書」と返ってくることはまずありません。体感的にはこんな感じ。
| 1位 | 2位 | 3位 |
| ゲーム (オンライン・スマホゲーム含む) | 動画視聴 | 体を動かす系or お絵描き |
「その次は?その次は?」と聞いていって、5位か6位にようやく読書が入ってくる印象です。
この状況で、「読む力」が自然に高まるのを期待するのは、なかなかに厳しいですね。
「本は好き」でも身近にない子どもたち
「じゃあ、子どもたちは本が苦手なのか?」
司書先生としての答えはNO!!
これは自信があります。
私の勤務校では朝読書を始め、本を手に取りやすい環境が整っています。
すると、自然と子どもたちは本に吸い寄せられていくのです。
中には、「読む力」が弱い子どもたちもいます。それでも、目をキラキラさせながら挿絵を絵本を眺めています。
司書先生目線ではありますが、「知りたい」「学びたい」という子どもたちの本能と、読書の相性はバッチリ。
では、なぜ読書や本と距離ができてしまうのか?
それはシンプルに身近にないから、というのが大きいように思います。
身近、というのは家にあるかどうかという意味合いとは少し違います。
いくら近くに本があっても、それ以上に魅力的なものがそばにあれば、自ずと本との距離は開きます。

子どもは本当に”好きなこと””楽しいこと”に正直で、しかも感が鋭い(笑)
彼らの身近に本をもっていくには、やはり大人の力が不可欠なのです。
「読む力」を育てるのは誰?
こうやって書くと、「読む力が育たないのは家庭環境のせいですよ!」と言われているように感じるご家庭もあるでしょう。
「家で本を買っても全然読まないんです。ちゃんと本棚に並べてあるのに。」
「読み聞かせは聞いてくれるけど、自分では読みません。」
そんな声もよく聞きます。
「読む力」を育てるのは誰なのか??
私の答えはみ〜んな!!
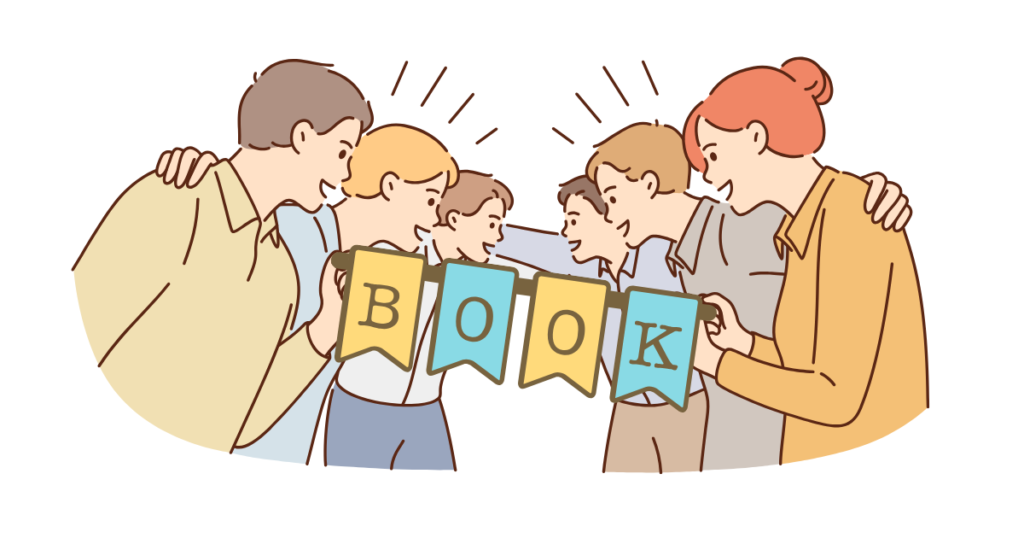
もう、身の回りの人、み〜〜〜んな!!
誰かに責任を押し付けて解決できる問題ではないのです。
だってそもそも、社会全体が読書となかよしとは言えないのですから、できる人が力を合わせてやるしかないのです(笑)
▶︎おうちの人
▶︎学校の職員
▶︎地域の本好きな方々
▶︎地元の書店
▶︎地元の図書館や公的な職員
実は、動画サイトにだって、読書の楽しさを少しでも広めようとしてくれているクリエイターもたくさんいます。出版社が解説している動画サイトもあります。
そうやって、少しずつ子どもににじり寄るようにして、地道に本を近づけていくのが近道なのです。
「選んで」「読める」子を育てるためにできること
子どもたちを取り巻く人たちで、にじにじと本をもって近づいていこう作戦が一番だと言いました。
じゃあ、具体的になにをすれば??
それを語り始めると異常に長い記事が出来上がるので、それぞれができる具体策は別記事にまとめるとして…。
絶対にコレが大事!ということがあります。それは…
大人が本を全力で楽しむ!!
子ども向けの本じゃなくてもいい。漫画でも絵本でもいい。
とにかく、大人が目を輝かせて本について語ったり本を推したりする様子が何よりの起爆剤になります。
ここで、事例をひとつ。
あまり本に興味がなさそうなAくん。
朝読書でも、とりあえず本を選んで開くものの夢中で読む、という雰囲気ではありません。
そんなある日、担任が熱く「こわい話」を語りました。
「この本に載っているこの話が怖くて忘れられなくてさ!ネタバレしていい?じゃあいくよ…。」
そうやって、身振り手振りを入れながら本の内容を説明。
しかもそのあとに、映像もいいけど、想像するのもすごく怖いんだ!と語り尽くしました
すると、次の朝読書のとき、Aくんは怖い話を真剣に読んでいるではありませんか!
「オレは全然怖くなかったぜ!」という感想付きで読み切っていました。
みなさんも、自分が語った本を友達や子どもが読んでくれた体験。
もしくは、人が楽しそうに読んでいる本や好きな人がおすすめしている本を読んでみたくなった経験はないでしょうか。
きっと、好きの気持ちを広げていくのが、何よりの”できること”なのだと思うのです。
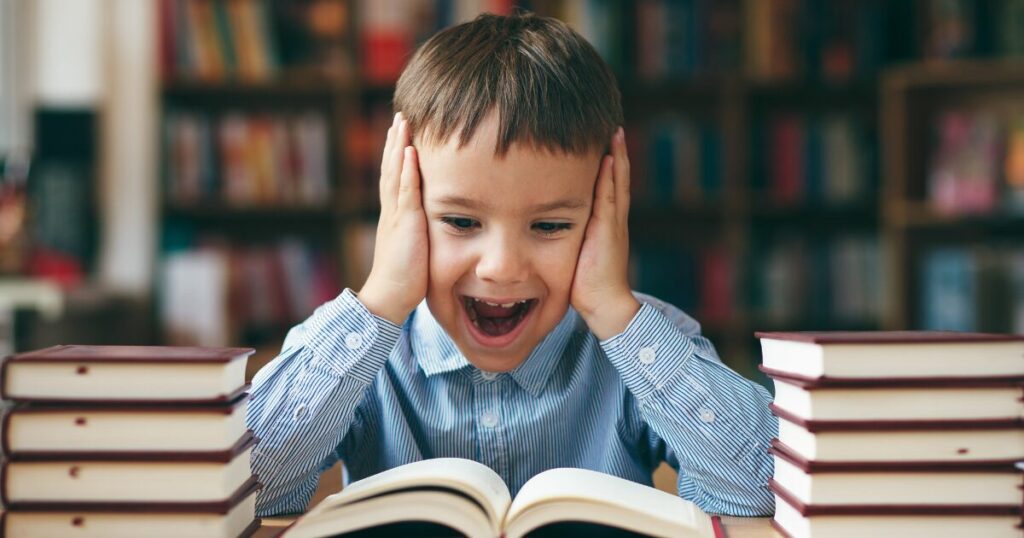
あなたの好きな本はなんですか?
あなたが保護者なら、難しい本でもいいから、ぜひ子どもに熱く語ってみましょう。
先生なら、一部だけでも子どもに読み聞かせてみましょう。
そして司書先生なら…図書室や学校全体を使って「私は本が好き〜!!!」と猛アピールしましょう(笑)
好きの気持ちが伝わった先に、「選んでみたい」「読みたい」があるのだと思います。
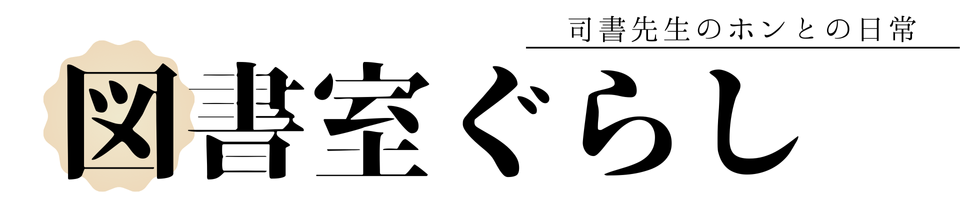
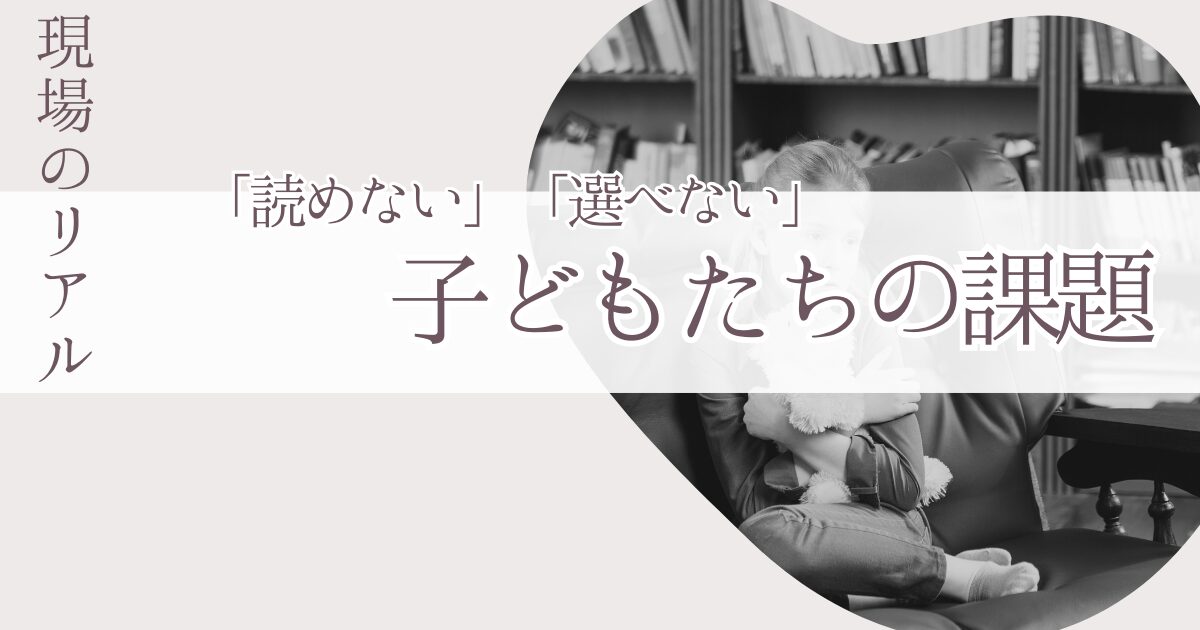
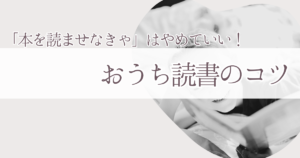


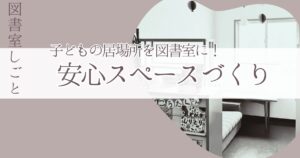
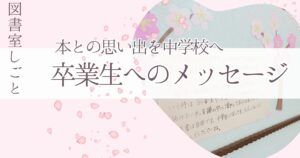

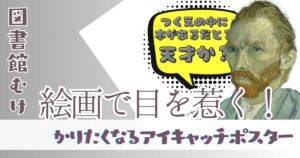

コメント